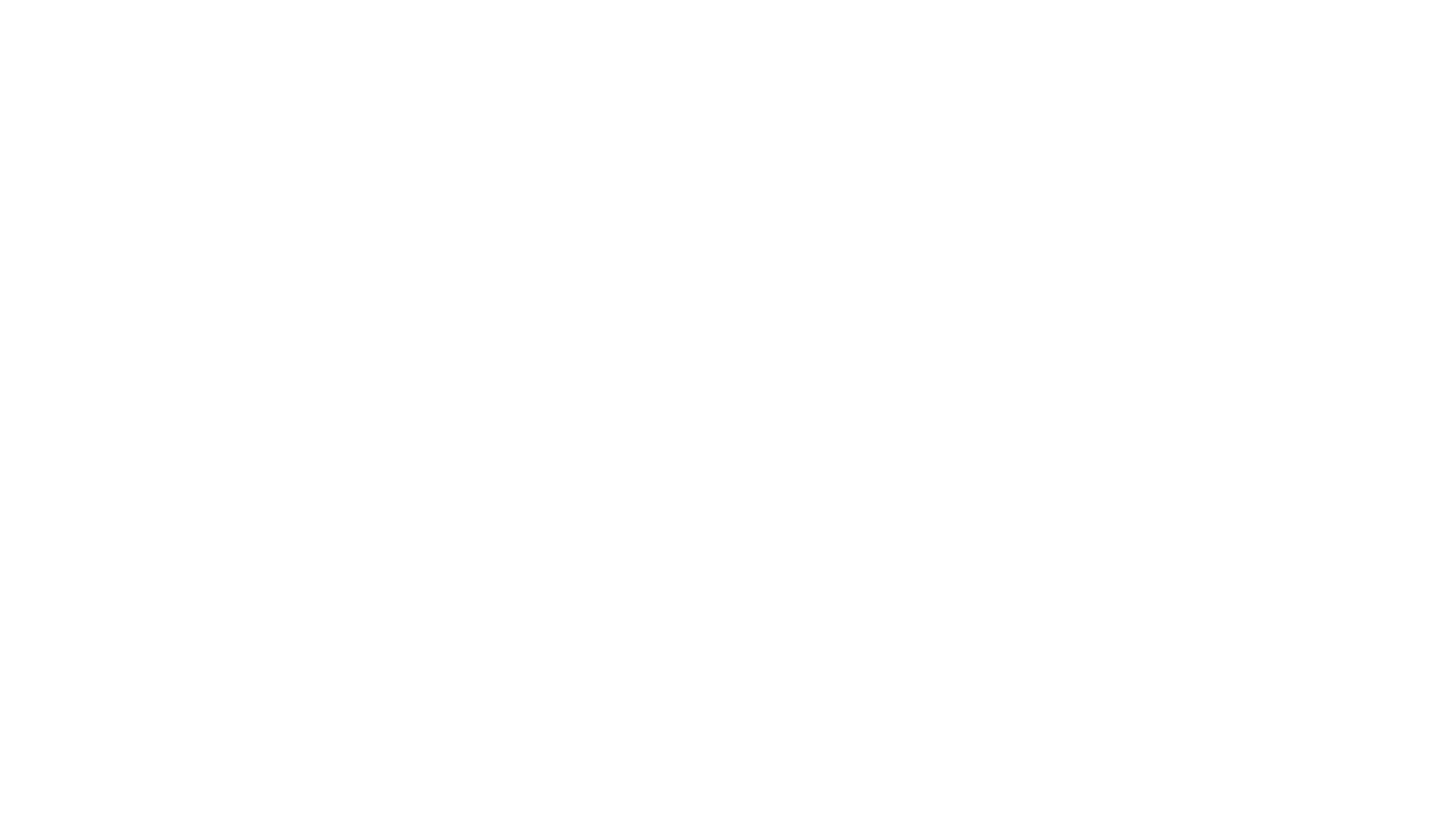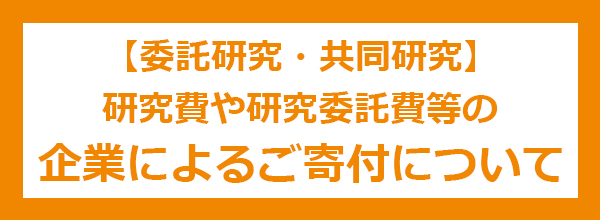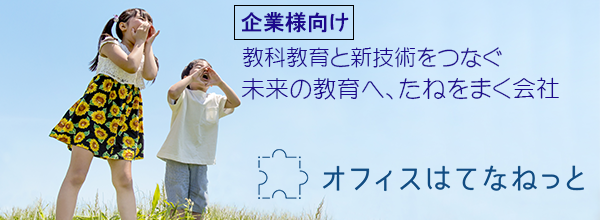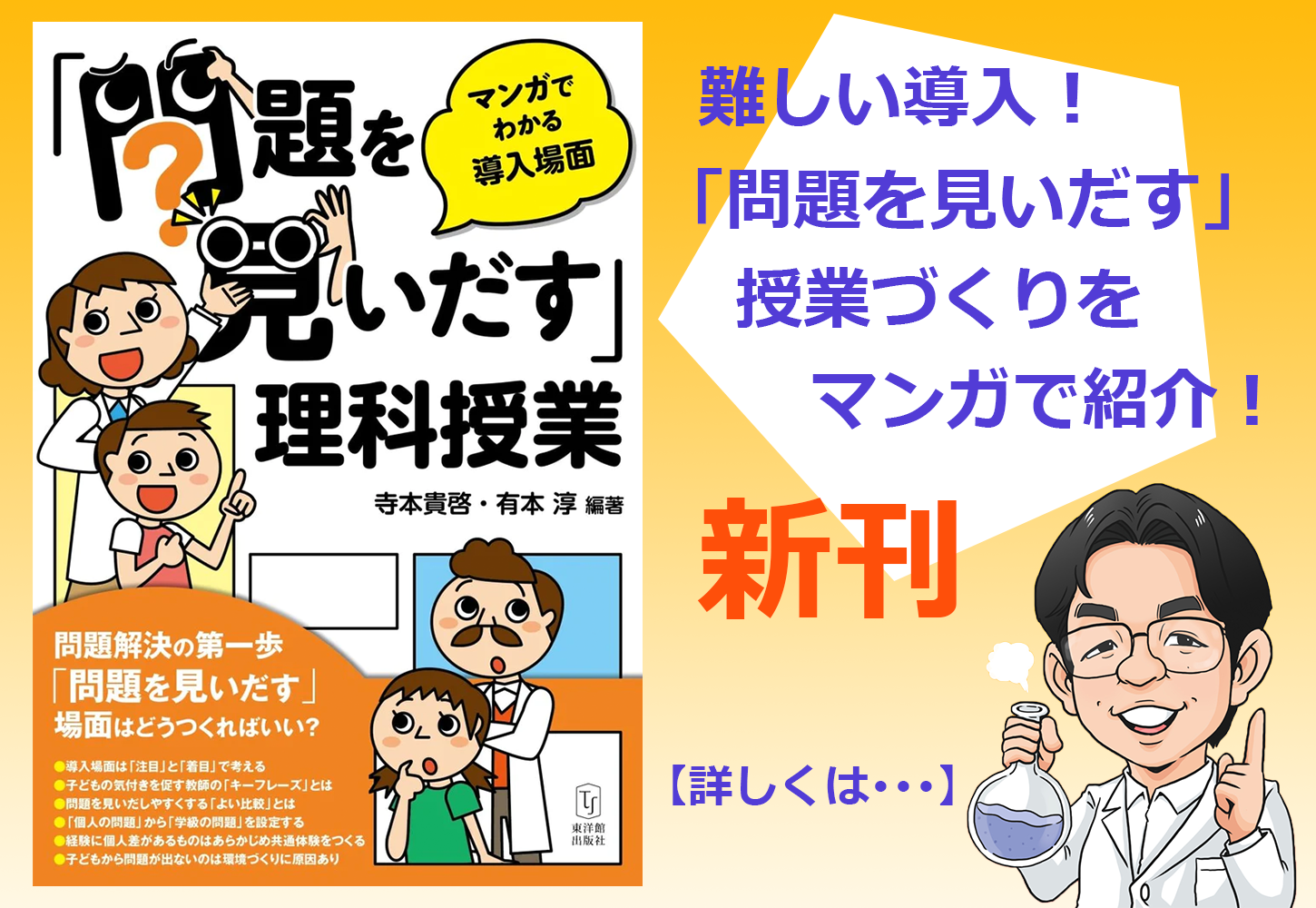掲載されました 理科の教育 2025年 02月号 (特集:子どもが問題を見いだすとき)
現行の学習指導要領では、小・中・高ともに全教科で探究的な学習が大切にされています。探究的な学習では、子どもが課題を見いだすことが主体的な学びを動かす鍵と考えられています。もちろん理科では、問題解決の過程でも探究の過程でも、自然の事物・現象の中から、子どもが問題を見いだすことを大切にしています。
学習指導要領解説理科編では、問題を見いだすことについて次のように記述されています。
○小学校では、育成を目指す問題解決の力として、第3学年で「差異点や共通点を基に、 問題を見いだす力」の育成を目指している。
○中学校では、教科目標である「科学的に探究する力」を育成するに当たり、各学年で重点を置く活動として、「第1学年では、自然の事物・現象に進んで関わり、その中から問題を見いだす活動」に重点を置いている。
○高等学校では、教科目標の(2)についての解説で「思考力、判断力、表現力等を育てるに当たっては、自然の事物・現象の中に問題を見いだし、見通しをもって観察や実験などを行い、得られた結果を分析して解釈するなどの活動を行うことが重要である」としている。
このように、子どもが自然の事物・現象の中から問題を見いだすことから始まる理科の授業をつくって いくことは、理科に携わる教師にとって取り組んでいくべき課題と言えます。自らが見いだした問題の解決に向かって目を輝かせている子どもたちの姿を見るとき、教師は子どもと共に理科授業の喜びを共有することができるでしょう。
それでは、実際に子どもはどのようなときに自然の事物・現象から問題を見いだすのでしょうか。教師はそのためにどのような工夫をしているのでしょうか。一口に「問題を見いだす」と言っても、苦労をしている先生方も多いでしょう。
本特集では、様々な実践を通して、問題を見いだす場面にまつわるアイデアを共有することを目指しています。
(『理科の教育』編集委員会)
令和7年2月号 通巻871号 2025/Vol.74
【特集】
子どもが問題を見いだすとき
■子どもが問題を見いだす授業がなぜ必要なのか
●子どもが問題を見いだすためにどこまで緻密に導入場面を考えるのか
-「注目」と「着目」で考え「導入場面の本質」を視覚化する「授業展開モデル」- 寺本 貴啓 5
●生徒はどのように問題を見いだすのか
-問題を見いだすきっかけと意欲の継続- 田代 直幸9
■子どもが問題を見いだす授業実践(小学校)
●やってみたいことを実現した先にある子どもの姿-第6学年「生物どうしのつながり・自然とともに生きる」- 中野 直人13
●「変数」に着目した問いを見いだす指導法
-変数を軸に体験活動から学習の文脈へと接続- 森川 大地16
●相互作用モデルから現象を捉える
-1人1実験から個別最適な学びの充実を目指して- 山口 義亮19
●自然に親しみ,問いを見いだす授業デザイン-第4学年「月と星」「ものの温度と体積」の実践を通して- 齋藤 照哉23
■子どもが問題を見いだす授業実践(中学校)
●中学気象単元での自己決定とメタ認知を活用して問題を表現化する指導
松本 浩幸26
●生徒が問題を見いだして課題を設定する授業づくり-中学校第3学年「遺伝の規則性と遺伝子」の実践を通して- 宮下 健太29
●中学校理科第3学年「運動とエネルギー」における課題設定
-ジェットコースターの設計を通じた課題設定- 藤本 博之33
●中学校理科でも実現可能な「問題を見いだす」学びの追究―自分の力で事象から問題を見いだし,探究可能な課題に変換する― 平澤 傑36
■子どもが問題を見いだす授業実践(高等学校)
●生徒が探究につながる疑問を見いだす授業の実践-実験結果の数値から疑問を生じる授業デザインの提案- 上村 礼子39
●高校生が問題を見いだすための教師の指導の工夫-通常の物理基礎及び物理の授業における電気に関する探究的な活動を通じて- 石川 真理代42
●生徒が問いを見いだすために何が必要か-疑問から問いへ変換する思考の順序性に基づく授業実践- 竹田 大樹45
連載講座
●『理科教育学研究』を授業に生かす
科学のテクスト読解による科学の学び
―小学校第6学年「燃焼の仕組み」の実践― 比樂 憲一 48
●生徒をひきつける観察・実験
ヒキガエルの幼生の血流,血球の観察 岡田 仁 50
●教材研究一直線
日本で南十字星を撮影する② 田中 千尋 52
●教材の隠し味
校庭の生物の観察「生物の声」~観察した生物になりきって
自己紹介,生物ミュージアムの開催~ 大久保 正樹 54
●Let’s Try!理科授業のDX
「1人1台端末」を活用して,「身近な樹木」と向き合う主体的な学びを!
縄 祐輔 56
●ダイバーシティ&インクルージョンを考える
日本語指導と教科教育の統合:外国ルーツの子どもたちの学びを支える方法
澤田 浩子 58
●概念構築を目指した探究型授業
~小学校4年生の電流の働きとの連結~豆電球の様子から
謎の4つの回路の配線を解明しよう「電流①」 荒尾 真一 60
●先生はサイエンスマジシャンNEXT
まさにエアコン!ゴム弾性の不思議 辻本 昭彦 62
会長候補者推薦について
63
オンライン全国大会案内
66
学会通信 68
次号予告 80
〈今月の表紙〉
ムフロン 学名:Ovis gmelini 偶蹄目ウシ科。野生の羊の中では小型の種類。繁殖期になると,オスは大きな角をぶつけて争う。
表紙写真:片平久央
表紙・本文デザイン:辻井 知(SOMEHOW)